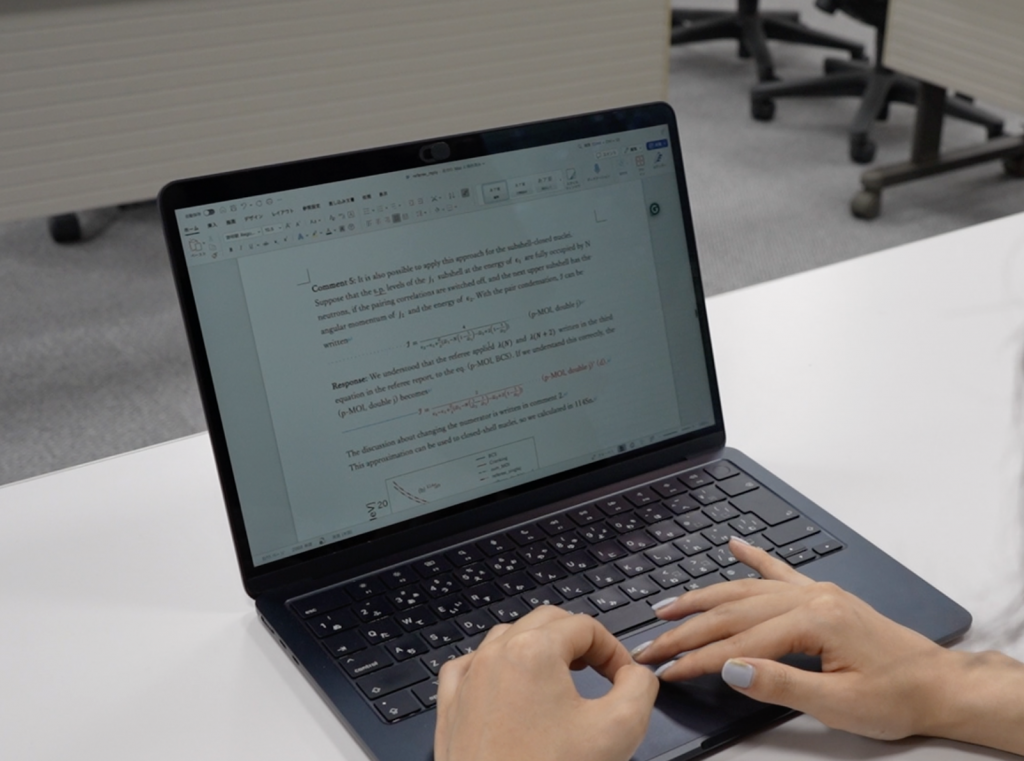筑波大学 数理物質科学研究群 物理学学位プログラム
原子核理論研究室 博士後期課程1年
(内容は、2025年7月取材当時のものです。)
どんな研究をしていますか?
コンピュータで行う数値計算を用いて、原子核物理を理論的に研究しています。
皆さんの目の前にある物質を細かくしていくと、原子という単位に分けることができ、その中心部分を原子核と呼んでいます。原子核は、陽子と中性子という2種類の粒子(核子)からなっており、その核子の数が偶数のものは、奇数のものに比べて質量が重く、安定しているといった性質があります。
このような性質の原因としては、原子核の中身が超電導状態(原子核を構成する粒子同士がドロドロに溶けあっているような状態)になっている核種があるからと考えられています。
そのような原子核について、超電導の理論や密度汎関数法という計算方法を用いて研究しています。
私の研究は、物理の研究でイメージされるような実験ではなく、物理の理論式を計算できるプログラムを書き、それをコンピュータ上で計算するといった理論的なアプローチで行っています。
なぜこの研究をしよう(専攻に進もう)と思ったのですか?
大学に入ってから、高校では触れてこなかった量子力学の分野にハマりました。量子力学は目に見えないスケールの物理を理解するのになくてはならない学問です。もちろん原子核を理解するためにも必要になります。目に見えないスケールで起きていることを説明する方法があることに感動して、原子核物理について研究したいと思いました。
研究の楽しいところと大変なところを教えてください。
量子力学を扱っているということが一番楽しいことではありますが、その他にも分野を超えて様々な物理の知識や考え方が必要になる点も魅力的だと思っています。原子核物理以外の分野の人達とも会話ができるのがすごく楽しいです。
一方で、元々数学や物理は苦手科目だったため、まず数学的な考え方を習得することや、物理の知識を身に着けることに苦労しました。計算もコンピュータで行うので、プログラミング技術が必要になります。ほぼゼロからプログラミングを始めたので、今でも大変な部分はありますが、研究室の先生方から丁寧に指導していただいています。
高校時代はどんな勉強をしていましたか?
学校の教科書やワークを使って、基礎的な部分から隅々までしっかり理解できるように頑張りました。テストで良い点を取ることよりも、勉強を楽しむことを優先していたと思います。その結果、苦手科目も得意科目も成長しました。高校での勉強が忙しく、塾には通いませんでした。苦手科目は自分一人で克服するのが大変だったので、高校の先生に何度も質問して対策していました。また、第一志望であった筑波大の過去問は何年分も解いていました。
数学・物理が苦手だったことはどのように克服してきましたか?
物理学科は、数学や物理が得意な人が多いイメージはあるかと思います。実際、数学・物理のセンスが良い人が周りに多く、苦しい思いをした時期もありました。それを克服できたのは、「好き」という気持ちがあったからだと思います。続けていくうちに知識や概念は身についていきました。逆に、国語が得意だったことが、研究の課題設定をきちんと論理立てて理解する力に繋がっています。苦手なことでも、好きな気持ちさえあれば、大学に入って何回でも学び直すチャンスはあると思います。
研究室の雰囲気は?
私の研究室は理論研究を行っている中でも人とのつながりが強い方で、穏やかな人が多く、尊敬できる先生もたくさんいます。お昼休みには研究室のみんなでご飯を食べに行ったりしていますね。先生方はかなり忙しいとは思いますが、それでも学生の質問や議論のために時間を空けてくださり、手厚い指導をしてくださいます。
研究室ではどのように過ごしていますか?
研究室では人によって生活スタイルが違いますが、私の場合は、朝10時には研究室に来て、夜19時くらいには帰るというルールを自分の中で決めています。研究と一口に言っても、先行研究を読んで、自分が何をしたいか考えて、実際に手計算をして、それを数値計算にのせて、結果を考察して…といったようにいくつかの段階があります。そのため、内容としては日々違うことに取り組んでいます。研究室全体では、週1回の輪読ゼミや興味あるトピックスをスライドにまとめて発表するといったセミナーが開催され、研究の議論の場となっています。
高校生に向けてメッセージをお願いします。
周りの人と自分を比べて落ち込まずに、自分が好きな学問や趣味を自由に見つけていってほしいです。大学での勉強や研究は、高校の科目と比べて幅広く、さらに深くまで学ぶことができます。きっと自分の興味のあるテーマが見つかると思うので、まずはいろいろな人の話を聞くことで、自分の視野を広げてみてください!
(文・広報サポーター 野本実奈)